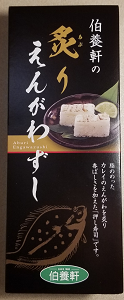小諸そば。首都圏を中心に出店しているそばチェーン店──
じゃなくて
本記事で紹介したいのは、「小諸駅のそば」です。長野県を走るしなの鉄道。その小諸駅に店を構える立ち食いそば屋『清野商店』。地元メディアの情報によると、しなの鉄道の社員が定年退職後にオープンさせた店だそうです。

元鉄道マンが営む立ち食いそばの実力はいかにっ!?
信州といえば「そば処」ですが、この店ではうどんも食べられます。でもまあ普通に考えて、だいたいの客はそばを注文するでしょう。私が訪れたときも、他の客は全員そば頼んでたし。
注文方法 自分で食券に注文を書き込み渡す(口頭でもOK)
『清野商店』は小諸駅の改札外に店があります。外から来た人は、入場券を買ってホームに入らなくても大丈夫。列車旅の途中で寄る場合は、いったん改札外に出なければいけません。
それでは食レポといきましょう。まず注文の仕方。

不鮮明な写真で申し訳ないですが、注文口に食券(紙の札)とペンが置いてあります。
この中から注文したい食券──たとえば「天ぷら」を選んで取り出し、そば or うどんにマルを付けて、代金と一緒に渡す仕組みです。
ただ、この食券じゃないと注文を受けてくれないわけではなく、口頭で注文しても大丈夫。実際、私のあとに来た人は、口頭で伝えていました。
でもまあ、店が食券を用意しているということは、それを使ってほしいわけですから、食券を渡した方がいいでしょう。
メニューはオーソドックスです。立ち食いでも高価格化が進み、原材料費高騰も叫ばれる中で、良心的な値段だと思います。(※2023年現在のラインナップと価格)
- かけ 350円
- 天ぷら 450円
- 月見 400円
- 天玉 500円
- 山菜 400円
- とろろ 400円
一人ずつ客を捌くので多少時間がかかるケースもありそう
昼時ですが、厨房にいたのは一人でした。こちらが元鉄道マンの店主さんでしょう。注文対応から調理まで、一人で作業されていました。店側の視点だと、オペレーションは以下の流れになります。
注文を受けて代金を貰う
→調理する
→商品を提供する
→次の客の注文を受ける。以下ループ
複数の注文を同時並行で捌くのではなく、一人ずつ対応・完結させていくのです。そのため、仮に3~4人が並んだ場合、最後尾の人は数分待つはずです。
ただ、店を少し眺めていて思ったのですが、そのスタイルは正解かと。
というのは、この店はカウンターで立ち食いする方式ですが、詰めて5人ほどのスペースしかありません。あまり迅速に商品を提供し、客を多く呼び込んでしまうと、カウンターがパンクして食べる場所がなくなります。
まさか丼を片手で持って、文字通り立ち食いするわけにもいかないし。
一人ずつ注文を捌く方式なら、一気に満席になってパンク、なんて事態にはなりにくい。繁盛し混雑しても、商品を受け取ったときには、先に注文した誰かは食べ終えている……という流れが作れます。
それを店主さんが計算して(=意図的に)やっているのかは知りませんが。
麺(そば)は冷凍だが不満はない
私はかけそばを注文しました。元鉄道マンの店主さんの仕事ぶりを眺めることにします。まず、冷凍庫から冷凍麺(そば)が取り出されました。
──などと書くと、「え~、せっかくの信州で冷凍麺? チェーン店でもないのに」とガッカリするかもしれませんが、生麺を使えばいいというものでもないでしょう。
店側としても、保管や作業効率の問題があり、早さや値段も含めたトータルパフォーマンスを上げるために、冷凍麺を使うのは普通にアリかと。
そもそも「冷凍 = 不味い」が偏見で、冷凍うどんなんかは、茹で立ての良い状態を急速冷凍しているのでじゅうぶん美味しいですよね。冷凍は時を止める魔法! ……とまでは言い過ぎか(^^;)
茹で上がったそばに、汁がかけられます。おもしろいと思ったのは、そば汁を鍋ではなく炊飯器に入れてあったところ。鍋で火にかけていると煮詰まってしまうので、それ防止のためでしょうか?
私が注文した、かけそばのトッピングはネギのみ。調理台のネギの容器にはフタがされており、都度フタを開けてネギを取り出していました。フタをしてあった方が、ネギが乾かないし、衛生面でも好ましいです。
「そんなん当たり前」と思うかもしれませんが、いちいちフタを開け閉めするのはメンドクサイじゃないですか。どの商品にも(たぶん)ネギを載せるはずで、このあと私の後ろで待っている人のそばも作るはず。だったら開けっ放しでいいやん、となるのが人間心理というもの。
私のように、そんな細かいところまで見てる客も、そういないだろうし(笑)
ネギの扱い一つにも、安きに流れない、丁寧な仕事をする姿勢が窺えました。
シャキッとしたそばと濃い汁がよくマッチ 個人的には好み
かけそばの到着です。1分で提供されるような早さは(もちろん)ないですが、「まだ~?」と思わされるほどの時間もかかりませんでした。

それではいただきます。ズルズル
これは俺の好きな味だ!
いい感じにそばがシャキッと引き締まっています。これは「茹でが足りなくて硬い」のではなく、しっかり茹でて中まで火が通されたうえでのものかと。スルスルと入ってきます。
そのため、食べていて口が疲れないです。
そば汁は関東系。濃い目の醤油タイプ。甘さは控え気味か。良い香りです。
こういう汁の場合、そばが柔らかすぎると汁の中に“埋没”するのですが、シャキッとした状態のため、そばの存在感が失われていません。麺と汁がよくマッチしていると思いました。
ごちそうさまでした。何か奇をてらっているわけではなく、スタンダードなタイプですが、駅そばレベルは高い方ではないでしょうか。じゅうぶん満足できました。
ただし、量は多くないので腹は膨れません。サイドメニューの類もない。必要なら大盛りを注文しましょう。普通盛りの場合は、食事ではなく、おやつ・小腹を満たすという感覚の方がいいかもしれません。
営業情報(2023年現在)
- しなの鉄道小諸駅 改札外なので入場券等なしで利用可能。逆に鉄道で訪れた人は、一度改札外に出ないといけない
- 営業時間 7:00~15:00
- 定休日 水曜日
鉄道グルメの他の記事もぜひどうぞ!
京阪電鉄の駅そば店『麺座』 優しいながらも満足感が得られる汁